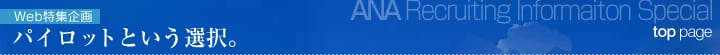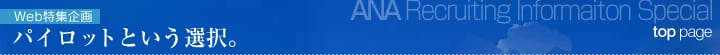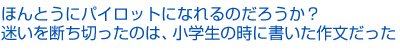
| 大学時代はラグビー部に所属し、4年間グラウンドで汗を流しました。キャンパスが幕張にあったので、空を見上げると、飛び立っていく航空機の機体が間近に見えるのです。そんなとき、父の田舎の九十九里の浜辺で、成田空港をめざし降下していく機体をながめていた、幼い頃を思い出すのでした。とはいえ、私がパイロットをめざそうとした直接のきっかけは、ラグビー部の先輩がANAの自社養成パイロットを受験し、合格したことでした。その先輩に話を聞き、文系の学生でも、特別な知識がなくてもチャレンジできることを知ったのです。採用試験をひとつひとつクリアし、合格の通知をいただいたときには、嬉しかったですね。でも次の瞬間、ほんとうにじぶんがパイロットになれるのだろうかという不安を抱くようになりました。そんな迷いを断ち切ってくれたのは、小学生の時に書いた作文でした。そこには「ぼくは大きくなったら、パイロットになりたい」と記されていました。そして私の目の前には、その夢に向かう道が開かれている。もう迷うことなく、突き進むだけだと決断しました。 |
|
|
 |
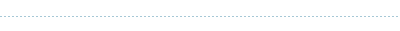

| 最初の基礎訓練課程では、ハイペースで講義が進み、1週間に1回くらいの頻度で試験が行われます。その試験をパスしなければ、その先はないわけですから、とにかく必死に勉強しました。特に、文系出身の私にとって、航空力学や電子機器などの科目は、講義だけでは理解できない部分も多くありました。そんなとき頼りになったのは、同期の存在でした。理系出身の同期に学び、逆にじぶんの得意分野については知識を提供する。互いに支え合いながら、チーム一丸となって同じ目標に向かっていく。まさにラグビーを通して学んだ精神、その大切さを訓練の過程においても思い知らされました。これからパイロットをめざすみなさんにお伝えしたいのは、けっして一人で孤立しないということ。訓練に入ったら、チームワークを大切に、みんなと協力、協調しながら、目の前の障壁をひとつずつ乗り越えてほしいということです。 |
|
|
 |
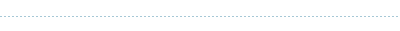
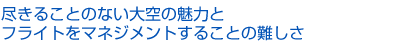
| 現在は、B747-400の副操縦士として、成田〜ロンドンなどの国際線に乗務する機会も増えました。操縦桿を握り、離着陸を経験する機会も多いのですが、離陸する瞬間の浮揚感、コックピットから望むパノラマ、着陸時の達成感など、パイロットでなければ味わえない感覚や経験も多く、ひとりの人間として純粋に感動できる瞬間もあります。反面、気象条件やお客様の体調の変化など、予期しないことへの対処をつねに求められる仕事でもあります。そのときどきの状況を十分に把握し、的確な判断をくだすためには、フライト前の入念な準備と日々の研鑽が欠かせません。副操縦士になりたての頃、「私には、コックピットから矢羽根(天気図の風速と方向を示す記号)が見える」というある機長の言葉に、驚いたことがありました。つねにじぶん自身を磨き、高めていこうという努力を積み重ねることによって、人は、それほどまでに可能性を広げられるのかと思ったからです。この11月から、ATPLという定期路線の機長になるための国家試験がスタートすることになりました。多くの機長から学んだ、技術と心を支えに、次のステップへと羽ばたいていきたいと思います。 |
|
|
 |
|