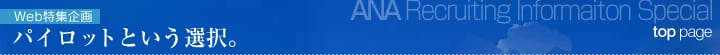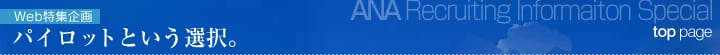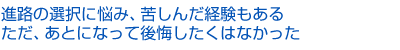
| 一般の大学から、パイロットをめざす道があることに気づかされたのは、私の尊敬する先輩が自社養成パイロットに挑戦したことがきっかけでした。その後、就職の時期になって、はじめて自分の将来ときちんと向き合い、浮上してきた選択肢のひとつがパイロットだったのです。とはいえ、具体的な準備をしていたわけでもなく、じぶんに適性があるのかも判断できません。ただ、空を飛ぶことを仕事するというのは非現実的な選択かもしれないけれど、そこには夢があるなと感じていたことは確かです。そして選考が進むにつれ、じぶんのなかにパイロットへの想いが強く大きくなっていくのを感じていました。当時の適性試験は実機を使用して行われていたのですが、初日に空酔いを経験したという苦い思い出もあります。ですから合格通知を受け取ったときには、喜びよりも驚きのほうが強かった。そして悩みもありました。すでに内定していた企業もありましたから、このままパイロットへの道をめざし、厳しい訓練を経て、その資格を得られるのだろうかと悩んだのです。結局、あとで後悔するよりもじぶんの力を試してみようとチャレンジすることを選びました。 |
|
|
 |
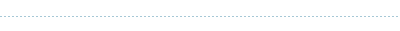
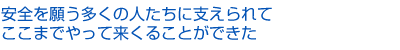
| 副操縦士となるまでの訓練期間、そして機長となるための昇格訓練。いずれも言い尽くせないほどの厳しさがありました。じぶん自身の限界に日々挑戦しているといった感覚があり、人生で最も勉強したのも、これら訓練期間中だったと思います。そうした厳しい日々を乗り越えてこれたのは、そこで得た技術なり知識なりが、結局は、すべて安全運航につながることだから。そして、同期の訓練生や教官、副操縦士時代にお世話になった多くの機長をはじめ、関係部署のスタッフなど会社全体として手厚いサポート体制が整っていたからだと感じています。ANAには、そうした風土が根付いている。私たちが最も大切にしなければならない安全性は、現場にいる一人の意識だけでは守り通せるものではありません。組織全体として安全を至上命題として取り組んでこそ、はじめて達成できるものでしょう。同じように、より優れたパイロットを育て、キャプテンとして活躍してもらいたいという全社的な想いに支えられて、ここまで歩んでこれたのではないかと考えています。 |
|
|
 |
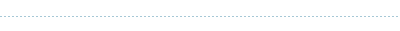
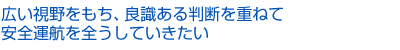
| 機長は、フライト中のいくつもの事象について次々と判断し、安全な運航を支えていくという役割を担っています。通常の運航であれば、それほど重大な判断に迫られることは稀でしょうが、それでもひとつひとつの判断には、とても勇気がいるのです。機長になって間もない頃には、それぞれの判断に躊躇しているじぶんをもどかしく感じたことさえありました。考えてみれば、それは機長の重責をそのまま表しているといえるかもしれません。確かな根拠をもとに、勇気をもって判断し、まわりに安心感を与えられる存在でありたいとつねに考えています。また一方では、機長というポジションに与えられた権限や力を意識し、その影響力にも配慮した発言や行動が求められています。ポジションパワーをじぶんの力だと勘違いするのではなく、広い視野をもち良識ある判断のできるバランスのとれた人間でありたいと心がけています。つねに技術と人間力を磨く努力を怠ることの許されない仕事ですが、その努力は、必ず報われる仕事だと感じています。夢のある大空へ、どうぞみなさんも挑戦してください。 |
|
|
 |
|