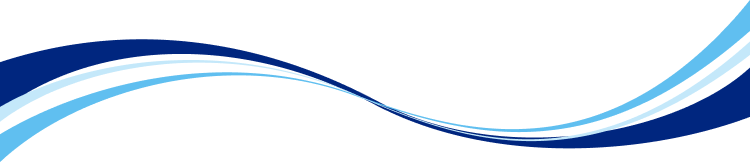
すべてのフライトに、
すべてを注ぎ込んで。
#運航乗務員(自社養成パイロット)
川島 明哲
ボーイング767機長(インタビュー時)
1992年入社 文学部英文学科卒業

Interview01
パイロットは
近くて遠い仕事だった。
私にとってパイロットは一番近くて一番遠い仕事でした。父親がパイロットだったこともあり、仕事自体は幼い頃から知っていました。しかし、父親の存在が大きすぎたため、自分には無理だと決めつけていたのです。国際線のフライトで家を空けることが多かった父親への反発もあったのかもしれません。本気でパイロットになろうと考えたのは就職活動を始めてから。改めて、自分の将来について考える中で、誇りを持ってイキイキと働いていた父親の姿が思い浮かんだのです。さらに、大学名に関わらず、誰でも挑戦できる点にも惹かれました。選考が進み、適性検査を受ける頃には「パイロットになりたい」という気持ちが非常に強くなっていました。ただ、父親は私以上に子供の合否が気になったようで、通知が届く時期になると自宅に郵便配達員が来るだけで落ち着かない様子だったようです。

Interview02
ANAに入社。
訓練を経て、大空へ。
アメリカ、ベーカーズフィールドでのボナンザによる初飛行は今でも忘れられません。エンジンを掛けた時から頭の中が真っ白になり、その後は自分自身の体が宙に浮いて、まさに空を散歩しているような感覚でした。それ以来、「空を飛ぶ」という魅力にすっかりとりつかれてしまったのです。副操縦士時代は今振り返ると、まだまだ半人前。毎回、「お客様の命を預かっている」と頭では理解しながらも、心のどこかでは常にコクピットの左側に座る機長に「守られている」という意識が残っていたと思います。また、この時期はパイロットとしての自信が生まれては消えるといったことのくり返し。百戦錬磨の機長たちとフライトを共にする中で、高度な運航技術はもちろん、人間としての格好良さ、器の大きさを目の当たりにすることも多く、目指している到達点の高さを実感する日々でした。

Interview03
機長に昇格。
初フライト後の安堵感。
10年8ヶ月の副操縦士期間を経ていよいよ機長に昇格。初めて機長として1日を無事に終えた時の安堵感は、副操縦士時代のそれとは比べ物にならないほど大きかったことをよく覚えています。また、「安全に絶対はない」という感覚も機長になってからのほうが圧倒的に強い。だからこそ、すべてのフライトで自分の精一杯を尽くしたと納得できる飛び方を心がけています。さらに、安全運航とひと口にいっても、その表現方法は機長の数だけ存在します。具体的には、毎回異なる運航環境に合わせて、「定刻」「コスト」「揺れ」などに対する意識のバランスをどうとるか。ここに機長ごとのこだわりが表れるのです。主役はお客様。お客様の数だけ求められているものは異なり、ニーズもその数だけ存在しているのがフライトです。私ができることは1便ごとに私自身が「一番やりたい!」と思った飛び方です。お顔を見ることができないコックピットドアの向こうにいるお客様に私の想いが伝わると信じて、誰よりもフライトを楽しんでいます。

Interview04
ANAのパイロット
であることに誇りを。
フライトは一期一会。刻々と変わる気象状況もさることながら、副操縦士やCAといったチームのメンバーもフライトの度に異なります。機長の発言や振る舞い、精神状態ひとつでチームのモチベーションに影響を与え、それがお客様に伝わることもある。そのため独りよがりにならず、チームで助け合い、チームでフライトを作り上げる意識を大切にしています。また、ANAには役員、上司、先輩、同期、後輩に関わらず、意見をぶつけ合う文化があります。パイロット同士が互いの技倆だけでなく、人間性まで意識し合い、切磋琢磨することで「ANAのパイロットである」という誇りを継承しています。これからパイロットを目指す皆さん。ANAでは人間性を重視しています。選考では、どんな人生を送ってきたかどうかを問われるでしょう。自信を持って答えられる毎日を過ごしてください。そして、最後まであきらめないでください。
