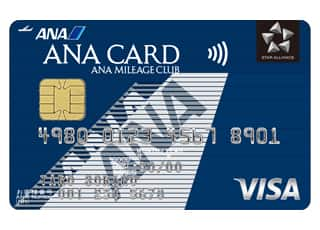冬でもおだやかな気候のなかで過ごせるのは沖縄の魅力のひとつ。日差しもやわらぐこの季節は、少し長めの滞在期間でゆったりと沖縄の食や文化、景色にふれて過ごす旅がおすすめです。夏の楽しみ方とはひとあじ違う、冬の沖縄ならではの過ごし方をご紹介します。
長めの滞在でじっくり楽しむプランが立てやすい季節
夏の定番リゾートとしてのイメージが強い沖縄ですが、冬にはこの季節にしかない沖縄の魅力があります。夏と比べて観光客が少なくなるこの季節、気候の良さに加え、ホテルなど宿泊施設の予約も比較的取りやすくリーズナブルに利用できることも。すこし長めの滞在がしやすいので、ゆったり"沖縄らしさ"に浸る旅にはぴったりの季節です。
旅の拠点となるホテルはプランに合わせて選びましょう。館内施設が豊富なリゾートホテルを選べば、旅の合間にさまざまなアクティビティが楽しめます。また、沖縄の自然を感じながらゆったりとした時間を過ごせるヴィラタイプの宿泊施設なら沖縄の豊かな自然を肌で感じて過ごすことができます。

写真:ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート

写真:MAKINA NAKIJIN
ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート
- 住所:沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260
- ウェブサイト:ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート
MAKINA NAKIJIN
- 住所:沖縄県国頭郡今帰仁村諸志2031-130
- ウェブサイト:MAKINA NAKIJIN
旬の沖縄の食材を堪能
ゴーヤー、もずく、海ぶどう、アグー、マンゴー、パイナップルと、実は食材が豊富な沖縄。それなら知らない食材もまだまだあるはず、ということで、沖縄で完全予約制のレストラン「Mauvaise herbe(モヴェズ エルブ)」を営む小島圭史さんに、冬の沖縄のおすすめ食材と、その味わい方を教えてもらいました。
小島さんはもともと、沖縄の旬の食材を使い、コース仕立てのフランス料理を出張スタイルで提供する出張料理人。現在は「Mauvaise herbe」のあるうるま市を拠点に、生産者や漁師・猟師と関わりながら日々沖縄の食材の探求を続けています。

写真:セソコマサユキ
沖縄で育つ野菜の特徴は、土壌からのミネラル分を多く含んでいること。四方を海に囲まれた沖縄の土壌は、サンゴが風化した礫土(れきど)でできていることや海水を含んだ雨が降りそそぐためカルシウムや鉄分などのミネラル分がたっぷり。また強い紫外線による抗酸化力から、味も色合いも濃いものが多くあります。
そんな沖縄の土壌が育む食材の中でも、小島さんのおすすめが沖縄在来種の「島大根」。沖縄の言葉でデークニとも呼ばれる島大根は、青首大根に比べて丸い形状でみずみずしく甘味が強いのが特徴で、12月から2月の冬の時期に楽しむことができます。丸焼きにした島大根をフランス料理の伝統的なステーキソース「ベアルネーズソース」であじわうのがおすすめだそう。

写真:セソコマサユキ
また、沖縄の魚というとイメージするのは青く美しい海を泳ぐ色彩ゆたかな魚たち。普段はなかなか見ることのない色鮮やかな見た目ですが、実は味が淡白で「脂は少ないものの、旨みを上げるための手立てを取ることで能力が格段に上がる」のだそう。他にも、秋から春前まであじわうことができる夜光貝も小島さんのおすすめ。
真珠層をいかした螺鈿(らでん)細工や、アクセサリーの素材として用いられることの多い夜光貝ですが、実はアワビやサザエに似た食感で食用にも向いています。おすすめは「デクリネゾン」。ひとつの素材をさまざまな調理方法で仕立てるフランス料理の基本的な考え方で、いわば夜光貝づくし。

写真:セソコマサユキ
そして、小島さんとっておきの冬に行きたいお店も紹介してもらいました。宜野湾市にある「Totto(トット)」は、沖縄の食材を使いイタリアンベースで仕立てる料理店。イタリアで学んだ後、地元である沖縄に戻り人気店の料理を担当、その後独立されたシェフのお店です。
「沖縄の今をしっかり捉えた素晴らしい料理」と小島さんが太鼓判をおすのは、コース料理の中の野菜の皿。それぞれの素材にふさわしい方法で丁寧においしさを引き出した料理は、沖縄の食材の底力を教えてくれるはず。旅行の工程が決まったら、ぜひお店の予約も忘れずに。

写真:セソコマサユキ
Mauvaise herbe
- 住所:沖縄県うるま市石川(予約成立後に所在地お知らせ)
- ウェブサイト:Mauvaise herbe
Totto
- 住所:沖縄県宜野湾市嘉数4-6-7
- Instagram:Totto
沖縄のアートやクラフトに向き合う
沖縄県には、琉球びんがた、八重山上布、三線など国指定の伝統的工芸品が16品目あり、古くから工芸品が暮らしに息づく土地。歩いて散策するのが気持ち良い冬の季節は、街歩きをしながらクラフトに触れる旅もおすすめです。
沖縄のクラフトの今に触れるなら、那覇市松尾にあるセレクトショップ「miyagiya」に足を運んでみてほしい。miyagiyaは店主・宮城博史さんが、古典的なやちむん(やちむんとは沖縄の言葉で焼き物のこと)だけでなく「今作られている新しい沖縄の器」を紹介したいという思いでオープンしたお店。店内にはつくり手と直接やり取りをして集めたやちむんなどの器や琉球ガラス、衣類、アクセサリーなどが並びます。

写真:セソコマサユキ
「沖縄のクラフトの特徴は、日常生活に根ざしているところ」と宮城さん。独自の技法や製法も大切に受け継がれていますが、それだけでなく毎日使うことを大切にして作られている作品が多いのだそう。だからこそmiyagiyaでも暮らしの中への取り入れ方や使い方の提案を積極的に行っています。例えばピッチャー。本来は飲み物を入れて注ぐための道具ですが、花瓶にしたりコーヒーをドリップする時のサーバーとして使ったり、ひとつの用途に限らない使い方を紹介しています。
また、個性豊かな沖縄のつくり手の中でも宮城さんが注目しているのが、「工房コキュ」の芝原雪子さん。やちむんの伝統的な作り方を継承しつつも、独創的な形や柄で新しい作品を生み出すつくり手です。また奥山泉さんは、沖縄県立芸術大学の彫刻科出身のアーティスト。表現の幅が広く自由奔放な作風の奥山さんの作品は、使いやすさもしっかりと兼ね備えているのだそう。独特でありつつも日常に溶け込む作品は、使う楽しさに気づかせてくれそうです。

写真:セソコマサユキ
さらに沖縄の歴史的なクラフトに触れるなら、miyagiyaから徒歩7分ほどの距離にある「那覇市立壺屋焼物博物館」に立ち寄ってみて。歴史的にも重要な作品が多数収蔵されていて、やちむんも年代ごとの色合いや質感の違いなどを確かめることができます。博物館のある壺屋周辺やmiyagiyaのある松尾周辺は、徒歩で往来ができる距離。近年新しいお店ができていたり、1本道を入るとまた違う雰囲気の通りが現れたり、歩いて散策するのにもおすすめのエリアです。

写真:那覇市立壺屋焼物博物館
miyagiya
- 住所:沖縄県那覇市松尾2-19-39
- ウェブサイト:miyagiya
那覇市立壺屋焼物博物館
- 住所:沖縄県那覇市壺屋1-9-32
長い夜を美味しいお酒と楽しむ
本島と比べると日が長いものの、18時前には日が暮れる沖縄の冬。沖縄のお酒「泡盛」で、ちょっと長い沖縄の夜を楽しんでみませんか。何度か沖縄を訪れていても、その度数の高さから泡盛にはまだ挑戦したことがない方も少なくないのでは。そこで琉球王朝時代1848年(嘉永元年)から続く首里最古の蔵元「瑞穂酒造」の仲里彬さんに最近の泡盛事情やおすすめの飲み方を教えてもらいました。

写真:瑞穂酒造
沖縄県出身の仲里さんは、お父さんがお酒好きだったこともあり、物心ついた頃から泡盛が身近にあったそう。大学では醸造学を専攻し、大学院の恩師のすすめや瑞穂酒造の社長 玉那覇美佐子さんとの出会いをきっかけに泡盛の世界に入りました。
泡盛の魅力は、なんといっても限定された製法の中でも風味の多様性があること。近年は特に新しい取り組みから生まれる泡盛が注目を集めています。県内の泡盛蔵12蔵の蒸溜家集団が手掛ける泡盛「尚」は、伝統的な1回蒸溜製法から3回へと蒸溜回数を重ねることで柔らかくクリアな飲み口を実現した泡盛の進化形。他にも、製造者・研究者・販売者が三位一体となって試験的な泡盛を開発、数量限定で製造・販売する「shimmerシリーズ」など新しいアプローチが行われています。

写真:南島酒販
さて、仲里さんおすすめの飲み方は、氷水に泡盛を少量浮かべて混ぜずにいただく「フロート」スタイルや、那覇市の小料理屋「小桜」発祥の泡盛の炭酸割り「Aボール」。すっきりとした飲み口のAボールは泡盛が初めての方にもおすすめ。ゴーヤーチャンプルーや豆腐ようといった沖縄料理にぴったりです。「小桜」では、「瑞穂酒造」の「尚」や「shimmer」も味わえます。また年数を経た良質な「古酒」に出会ったら、食後小さな酒器(ちぶぐゎー)に入れて、時間経過による風味の変化を楽しみながらゆっくり味わってみて。

写真:小桜
またここ数年、県内の泡盛の酒造所で活発なのが、さとうきびや黒糖といった沖縄の素材を活かしたラムやジン造り。瑞穂酒造でも170周年を迎えた2018年以降、ラムやジン造りに力を入れています。「世界で認知されているラムなどのお酒を、沖縄の原料(さとうきび、黒糖)を元に造り、世界的な評価を受けることで沖縄の魅力発信につながり、ひいてはバックボーンにある日本最古の蒸溜酒"泡盛"へ、世界中の方に目を向けてもらえるきっかけになると考えています」と仲里さんは話してくれました。
まだまだ奥が深そうな沖縄のお酒事情。もっと知りたいと思ったら、仲里さんが「沖縄のお酒を世界レベルのクオリティで楽しめるお店」と話す、那覇市にあるEl Lequio(エルレキオ)へ。アジアベストBARにもランクインしたこのBARで、泡盛など沖縄のお酒とじっくり向き合ってみてはいかがでしょうか。

写真:El Lequio
瑞穂酒造
- 住所:沖縄県那覇市首里末吉町4-5-16
- ウェブサイト:瑞穂酒造
小桜
- 住所:沖縄県那覇市牧志3-12-21
- ウェブサイト:小桜
El Lequio
- 住所:沖縄県那覇市安里1-3-3 安里家ビル 1F
- Instagram:El Lequio
冬の沖縄ならではの景色を探しに
冬の沖縄には、冬にしか見ることができない景色があります。沖縄の冬の風物詩といえば「ホエールウォッチング」。12月下旬から4月上旬はホエールウォッチングのベストシーズンです。夏の間シベリア海域で暮らしていたザトウクジラは、冬になると出産と子育てのために暖かい海を求めて慶良間諸島近海にやってきます。船でのツアーに参加すれば、間近で迫力満点なザトウクジラを観察することができ、また読谷村にある残波岬からは運が良ければ肉眼でもクジラを見ることができます。

また、冬の景色ではずせないのが桜。本島では春を告げる花のイメージがある桜ですが、沖縄での開花時期は1月下旬から2月にかけて。あざやかな濃いピンクの花をつける寒緋桜(カンヒザクラ)でひと足早いお花見が楽しめます。特に世界遺産の今帰仁城跡は桜の名所として有名で、城跡内で開催される「今帰仁グスク桜まつり」には毎年多くの観光客や地元客が訪れます。

夏のイメージが強い沖縄の海ですが、実は地元の方にとっては冬の海こそが好きな景色だったりします。天気が良い日は海の色がやわらかく綺麗で、地元民が通う海岸では三線を弾くおじさんに出会えるなんてことも。また西側の海岸沿いでは広大な海に沈んでいく夕日を眺めることができます。穏やかで静かな冬の海で、時間を忘れてのんびりと眺めて過ごすのもおすすめ。

写真:セソコマサユキ
穏やかな気候で、夏とは違った魅力にあふれる冬の沖縄。のんびりとまち歩きを楽しんだり、レンタカーを借りて少し遠くの自然と戯れたりしつつ、じっくり"沖縄らしさ"を探す旅に出掛けてみませんか?
- 記載の内容は2024年11月現在の情報です。変更となる場合があるのでご注意ください。