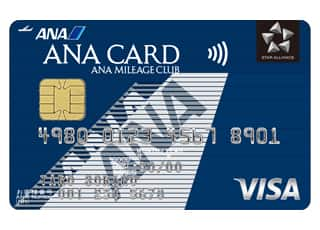「熊本県・天草」釣り旅の記録
“深紅の宝石、誉れ高き湯島マダイを釣り上げる”
秋丸さんは普段、地元の福岡からも近い玄界灘でタイラバをすることが多い。
同じ九州のマダイ釣り場でも、外洋に面した玄界灘に比べると、内海にあたる島原湾はねらう場所の水深が大きく変化する所が多くある。また、潮の流れが非常に速くなる場合がある点が特徴と感じているとのこと。
それらを意識した釣りを心掛けていた。
タイラバ釣りの基本は、船長の合図が出たら海底までまずしっかりタイラバを沈め、あとはゆっくりリールで巻き上げるというもの。
とても単純だが、どの水深まで巻き上げるか、どのくらいの速さで巻き上げるかで魚の反応に差が出る。
また、巻き上げを遅めにする場合も速めにする場合も、速さ自体は一定に保たないと釣れないのも大きな特徴だ。慣れるまではこれがなかなか難しいが、とはいえ、初めての人でもできないことはない。
船長が指示する水深まで巻き上げたあとは、再び海底に落とす。タイラバは着底したあと、間を置かずに巻き上げるほどマダイが違和感なく食うともいわれている。
このように、タイラバは操作が第一とされるが、同時にヘッドやスカートの色によっても反応のよさが変わってくる。
定番カラーとされるのは、赤、ピンク、オレンジ、緑など。
当たりカラーをいち早く見つけられれば、連続ヒットという幸運も訪れる。

この日、満潮から干潮に向かう時間帯から釣り始めた秋丸さんと岡田さんは、小型のマダイ、キジハタ、アオハタ、ヒラメと早々に魚の引きを楽しめた。ただ、これはというグッドサイズのマダイはなかなか顔を見せてくれない時間が続いた。
チャンスが来たのは干潮から満潮に向かう上げ潮になった時。
海の魚たちは、こうしたタイミングでエサを活発に追うことがよくある。
いろいろな巻き上げ速度を試しながら、魚の反応が少ない時間帯も集中力を保ち続けていた秋丸さん。
すると「コツコツ」という、タイラバ特有のついばむようなアタリがイトをとおして手もとに伝わって来た。しかし、この段階ではまだ合わせない。そのままリールを巻き続け、ズシッとしっかりとした重みが乗ったところで、満を持してロッドを動かし魚の口にしっかりハリを掛ける。



大ダイを釣り上げたのは、タングステン製で100gのヘッドを付けたタイラバ。
そして、秋丸さんはこのタイラバのネクタイ部分をあらかじめ短くカットしていた。
これはマダイがタイラバを食いきらないような状況で有効なテクニックの1つ。
「みっぴさん、すごい!」と岡田さんも脱帽の一尾だ。


釣り経験豊富な秋丸さんの工夫が見事に功を奏した



- このコンテンツは、2016年10月の情報をもとに作成しております。