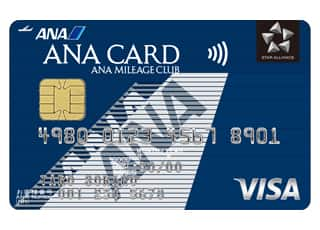上方芸能を楽しむ1日を旅のアクセントに
関西エリアの中心地・大阪は、古くから栄えた商業都市。グルメやショッピング、最新のエンタメが集まり、旅先としても魅力的ですが、一方で長い歴史に育まれた文化が息づいている場所でもあります。特に注目したいのが、江戸時代に生まれた「上方落語」と「人形浄瑠璃文楽」。大阪人の温かい人柄が感じられるこの二つの上方芸能を通して街の奥深さを感じる1日は、大阪の旅をより記憶に残るものにしてくれるでしょう。

上方落語の聖地「天満」エリアで大阪の下町風情を体感
上方落語とは、江戸時代中期、大阪・京都を中心に神社の境内や屋外の広場などで演じられた辻噺(つじばなし)を起源とし、華やかな演出と誰でも親しみやすい日常的なネタで愛されてきた落語のスタイル。関西を代表する芸能の一つです。
その上方落語を楽しめる定席「天満天神繁昌亭」があるのが、キタの中心地「梅田」に隣接する天満エリア。商業施設が集まる都会から、電車でたった一駅先とは思えない昔ながらの下町風情が広がり、大阪らしい活気とともに上方落語の魅力を体感できるエリアです。

舞台と客席が一体となって笑いの輪に包まれる「定席」
「天満天神繁昌亭」は、大阪で唯一の年中無休で上方落語を楽しめる定席。戦後、途絶えてしまった寄席を復活させるため、市民や落語ファンの熱意と寄付によって2006年に誕生しました。この劇場がある界隈は、かつて「天満八軒」と呼ばれ、多くの寄席や演芸場が立ち並んでいた場所でもあります。そんな聖地で、上方落語の魅力や繁昌亭の楽しみ方について上方落語協会 会長・笑福亭仁智さんにうかがいました。

「主に座敷で噺を聴かせることが多かった江戸落語に対して、にぎやかさが特長の上方落語は神社の境内で生まれた"辻噺"が始まりです。ネタの最中に三味線や鳴り物といったハメモノと呼ばれる効果音が入ったり、歌舞伎をパロディにしたようなネタがあったりするのは、その名残です」
「特に上方落語の古典は誰でも共感できる庶民的な題材が中心です。どうしようもない"ダメな人間あるある"を、ほんまにあほやなぁと笑い飛ばして包み込んでしまう、そんな温かさも醍醐味です」と仁智さん。
大阪といえば、江戸時代から商売人の街。中心地として栄えてきた船場の商人が登場するネタが多く、昔ながらの粋な大阪弁や、今も受け継がれるサービス精神旺盛な大阪人気質に触れられるのも上方落語の大きな魅力です。

「今や上方落語は映像でも気軽に楽しめる時代ですが、やはり生の舞台とは天と地の差があります。噺家はその場のお客さんの反応を見ながらネタを選ぶので、みんなで"笑い"を一緒に創り上げていくようなものです。時間が経つにつれて、一人一人の笑いが波のように広がり、やがて劇場全体を包み込む一つの大きな笑いへとつながっていく。この笑いを共有する生の醍醐味を、ぜひ劇場で体感してほしいです」と仁智さん。
そんな繁昌亭では、昼席(ひるせき)は週替わりで若手から大御所まで10組が登場します。うち8組は落語、残りの2組は色物と呼ばれる漫談やマジックなどを披露。一方、夜席(よるせき)は日替りで一門会や独演会が中心です。
「古典落語はもちろん、私のように新作落語で社会問題をユーモアで風刺するような噺家もいます。スタイルも語り口も多彩なので、まずは昼席でお気に入りの噺家を見つけて、次は夜席でじっくり楽しんでいただけるとうれしいです」
天満天神繁昌亭
- 住所:大阪府大阪市北区天神橋2-1-34
- ウェブサイト:天満天神繁昌亭
寄席とともに上方落語ゆかりの街を歩く
観劇前後に立ち寄りたいのが、大阪の庶民に「天満の天神さん」として親しまれてきた「大阪天満宮」です。お正月によく披露される古典落語"初天神"の舞台であり、実は「天満天神繁昌亭」が建つのも、大阪天満宮の敷地内。天暦3年(949)に創建され、学問の神様として信仰を集める菅原道真を祀る由緒ある神社で、今も受験生や学問成就を願う多くの参拝者が訪れています。

参拝を済ませたら、境内の北側にある「星合の池」へ足を運んでみましょう。橋を渡った奥には、上方落語の復興に尽力した六代目笑福亭松鶴、三代目桂米朝、三代目桂春團治、五代目桂文枝らを祀る「髙坐招魂社」があり、噺家たちにとっても特別な場所。「繁昌亭の出番や大切な公演前には、天神さんとあわせて必ずお参りします」と仁智さんも大切にしている場所です。

大阪天満宮の参道として栄えた「天神橋筋商店街」は1丁目から7丁目まで、南北約2.6kmにわたって続く関西一長い商店街。このエリアの楽しみがギュッと詰まった名物商店街で、ぜひ立ち寄りたい場所です。

約600店舗が軒を連ね、食べ歩きを楽しむのにぴったり。たこ焼きや串カツといった大阪グルメに加え、レトロな喫茶店や老舗の立ち飲み店など、個性豊かな店がずらり。細い路地にまで隠れた名店がひしめき、迷い込むような感覚で歩いているだけでもワクワクします。気さくな地元の方との交流が楽しめるのも旅の醍醐味です。
大阪天満宮
- 住所:大阪府大阪市北区天神橋2-1-8
- ウェブサイト:大阪天満宮
天神橋筋商店街
- 住所:大阪府大阪市北区天神橋1~7
- ウェブサイト:天神橋筋商店街
笑福亭仁智さんに聞く!観劇前後のほっとひと息
「せっかく劇場に来たなら、天満の美味しいもんも味わってほしいね」と仁智さん。普段から利用しているという近所のカフェと和菓子店を教えてくれました。
「words cafe.」は天満天神繁昌亭から徒歩数分にあるカフェ。ラジオ局「FM802」やテレビ局「関西テレビ」も近くにあるため、噺家だけでなく、多くのアーティストやタレントが訪れるそうです。

注文ごとに焼き上げる熱々のアップルパイが話題ですが、創業当時からの看板はボリューム満点のカツサンド。カリッと焼かれた薄めのパンに、分厚いカツが豪快に挟まれています。「楽屋の差し入れにもよくいただきますが、ひと口サイズにカットされているので、出番前にパクッと食べられるのが良いんです」。ちなみに、仁智さんのイチオシはエビフライカレー。「さらりとしたルゥが好みで、辛すぎずマイルドな味わいがクセになります」

「御菓子司 薫々堂(くんくんどう)」は天神橋筋商店街に構える元治元年(1864)創業の老舗和菓子店。かつて大阪天満宮の蛭子門前に店を構えており、天満宮の梅の香りが「くんくん」と薫ってきたことが、店名の由来だそう。「どれもおいしいですが、店主が大の落語好きで、落語ゆかりの和菓子がたくさんあるんです」と仁智さん。
例えば、夏から秋限定の「千両みかん」。「夏でも時期外れのみかんが食べたいという若旦那のわがままのために使用人が奔走する」という噺にちなみ、ミカンが爽やかな葛切りを考案。秋から春には、上方落語の演目"ちりとてちん"を題材にしたどら焼きなど、季節ごとに落語ゆかりの和菓子が登場します。
「繁昌亭せんべい」は、「笑って角なく、丸く円満に過ごし、日々繁昌してもらう」との願いが込められたもの。優しい甘みが特長です。

words cafe.
- 住所:大阪府大阪市北区天神橋2-5-18
御菓子司 薫々堂
- 住所:大阪府大阪市北区天神橋3-2-27
人形浄瑠璃文楽の発祥地「なんば」エリアで作品の世界観に浸る
大阪生まれの「人形浄瑠璃文楽」は、「太夫」「三味線」「人形」の三業が一体となった総合芸術です。ルーツは江戸時代初期のあやつり芝居。竹本義太夫や近松門左衛門を源流とする人形浄瑠璃芝居の中でも、明治期から一世を風靡した植村文楽軒の文楽座にちなみ、そのまま「文楽」と呼ばれています。
そんな文楽の上演を主目的とする「国立文楽劇場」があるのが、ミナミの中心地「なんば」エリアです。「大阪松竹座」や「なんばグランド花月」など、上方芸能の拠点が集まり、まさに関西エンタメの中心地。観光名所として知られる道頓堀は、かつてNYのブロードウェイのように芝居小屋が建ち並び、文楽が生まれた歴史ある場所です。周辺にはゆかりのスポットが点在し、観劇とともに巡ることで作品の世界観にひたることができるエリアです。

太夫、三味線、人形…文楽の楽しみ方は自由!
人形浄瑠璃文楽の起源は貞享元年(1684)、竹本義太夫が道頓堀に「竹本座」を開いたことに始まります。座付き劇作家の近松門左衛門が、"曽根崎心中" "女殺油地獄"など数々のヒット作品を生み出し、一大ブームを巻き起こしました。
道頓堀からほど近い日本橋に昭和59年(1984)に開場したのが「国立文楽劇場」。文楽の上演を主目的にした日本で唯一の劇場です。地元出身で界隈をよく知る劇場の営業課 課長・中澤久富さんに、文楽や劇場ならではの楽しみ方をうかがいました。

「文楽と聞くと人形芝居をイメージされるかもしれませんが、物語を支えるのは三業と呼ばれる、太夫、三味線、人形の三者です。一人で登場人物のセリフから物語のストーリーまですべてを語り分ける"太夫"、それに寄り添うように心情や情景を表現する"三味線"、3人が息を合わせてあやつる"人形"。この三業が一体となり、時にダイナミックで、時に繊細なドラマを紡ぎ出します」と中澤さん。
世界にも類まれな「三業一体の芸能」が日本独自の総合芸術として評価され、2008年にユネスコの無形文化遺産に登録されました。「こう聞くと敷居が高く感じるかもしれませんが、もともとは庶民の娯楽。気負わず、自由に楽しむのが一番です」
「おおまかなストーリーは観劇前に頭に入れておくのもおすすめですが、楽しみ方は人それぞれです。物語をじっくり追うのもよし、人形の表情や衣装の美しさ、迫力ある三味線の音色に注目するのもよし。太夫が音楽的に語る義太夫節には、江戸時代の言葉やイントネーションが引き継がれているので、昔ながらの大阪弁のエッセンスを感じられます。当時の観客の価値観を想像するのも面白いですよ」

文楽作品は、大きく分けて「時代物」「世話物」「景事」の3種類。「時代物」は江戸時代より前の歴史上の人物や事件を題材にしたもの、「世話物」は江戸時代の庶民の暮らしを描いた作品、「景事」は踊り中心の演目です。
「初めての方には"世話物"がおすすめです。大阪の街を舞台にした作品が多く、庶民の恋愛模様や街で起きた事件などを題材にしているので、共感しやすいんです。近松門左衛門の代表作"曽根崎心中"もその一つです」と中澤さん。

さらに、文楽のために設計された「国立文楽劇場」は、後方の席からも舞台が見やすいように1階席のみの731席とコンパクトな造り。舞台も緻密に計算されていて、人形がまるで地面に立っているかのように見える工夫が施されています。
観劇前や休憩中には、ぜひ1階の資料展示室へ。文楽の歴史を学べる資料、人形や衣裳などの舞台道具に加え、本公演中に登場する特設コーナーも必見です。
国立文楽劇場
- 住所:大阪府大阪市中央区日本橋1-12-10
- ウェブサイト:国立文楽劇場
観劇とともに作品ゆかりの大阪の街を巡る
「劇場の周辺には、文楽作品にも登場するゆかりのスポットがたくさん点在しています。舞台の余韻に浸りながら街を歩けば、作品の世界がより身近に感じられるはずです」と中澤さん。
まず訪れたいのが、劇場から徒歩約7分の場所に鎮座する「生國魂神社」。近松門左衛門作の心中悲劇"曽根崎心中"では、主人公のお初と徳兵衛がここで再会するシーンから物語が始まります。約2,700年前に創祀された大阪最古の神社で、"いくたまさん"との愛称で親しまれ、大阪の総鎮守として人々の暮らしを見守り続けてきました。

画像提供:生國魂神社
緑が清々しい境内には多くの摂社・末社が集まり、それぞれ異なるご利益があるとされています。なかでも注目したいのが、竹本義太夫や近松門左衛門など、文楽の成立に尽力した"浄瑠璃七巧神"たちを祀る「浄瑠璃神社」。芸能上達の神として信仰を集め、境内には“曽根崎心中”のお初と徳兵衛が描かれた絵馬も奉納されています。

また、実は上方落語が生まれたのが、この「生國魂神社」の境内。江戸時代、上方落語の始祖とされる米澤彦八が境内で辻噺を披露し、参拝者たちを笑わせました。その伝統は現在にも受け継がれ、毎年5月には「彦八まつり」が開催され、全国の落語ファンが訪れます。
「劇場から歩いて約10分の場所にある"高津宮"も、ぜひ立ち寄ってほしいスポットです。文楽の夏芝居"夏祭浪花鑑"のクライマックスは、この高津宮の夏祭りが舞台となっています」と中澤さん。

画像提供:高津宮
高津宮の創建は平安時代前期の866年。大阪発展のもとを築いたとされる仁徳天皇をお祀りしている由緒ある神社です。上町台地の高台に位置し、江戸時代には大阪湾まで見渡せる絶景の地でもあったそう。
ここもまた、上方落語とも関係が深い場所。古典落語「高津の富」「高倉狐」「祟徳院」の舞台としても登場し、現在も境内にある「高津の富亭」で、五代目桂文枝一門をはじめ、さまざまな落語の寄席が定期的に行われています。
もう一つ、忘れてはならないのが、文楽の源流ともいえる道頓堀の竹本座跡。今ではすっかり観光名所として有名ですが、ビルの合間にひっそりとたたずむ石碑が界隈の歴史を伝えています。

難波大社 生國魂神社
- 住所:大阪府大阪市天王寺区生玉町13-9
- ウェブサイト:難波大社 生國魂神社
高津宮
- 住所:大阪府大阪市中央区高津1-1-29
- ウェブサイト:高津宮
竹本座跡
- 住所:大阪府大阪市中央区道頓堀1-8
中澤さん&文楽座技芸員に聞く!観劇後の大阪グルメ
「劇場の近くには、大阪を代表する名店が集まっています。観劇の余韻にひたりながら、ぜひ大阪グルメを楽しんでください」と中澤さん。まず足を運びたいのが、お好み焼きの老舗「お好み焼き おかる」。店名の「おかる」は、文楽三大名作のひとつ"仮名手本忠臣蔵"に登場する勘平の恋人おかるに由来しています。
昭和21年(1946)創業で、実は中澤さんが学生時代にアルバイトをしていた思い出の場所。「山芋を使わず、あっさりとした昔ながらのお好み焼きを味わえます」。一番人気はお好み焼きスペシャルで、卵2個、豚やミンチ、海鮮などの具材がたっぷり入っています。見事なマヨアートは30年ほど前、2代目の安達佳代子さんがお客さんを喜ばせるために始めたものだそう。目でも舌でも楽しめる大阪人のサービス精神が詰まった一枚です。

「文楽が生まれた道頓堀にも、歴史ある名店がたくさんあります」と中澤さん。メイン通りの道頓堀商店街に構える昭和21年(1946)創業のうどん店「道頓堀 今井 本店」は江戸時代に芝居茶屋として始まり、道頓堀の歴史とともに歩んできました。
看板メニューは、ふっくらとした甘いあげが2枚のった「きつねうどん」。北海道産の天然真昆布と、九州産のさば節・うるめ節を合わせたコク深いだしが特長で、やわらかくもちもちとした大阪うどんと相性抜群です。

画像提供:道頓堀 今井
道頓堀でひと際目を引く重厚な木造建築の「はり重 道頓堀本店」も、大阪を代表する名店の一つ。大阪・堺で精肉店として創業し、道頓堀に移ったのは戦後の昭和23年(1948)。「当時、芝居小屋や劇場が立ち並ぶ道頓堀では、観劇とともに"はり重"で食事をするのがハレの日の贅沢だったそうです」
「はり重」のこだわりは黒毛和牛の雌牛のみを1頭買いすること。特にすき焼きコースが絶品。その上質な肉の味を最大限に引き出すため、牛骨を長時間煮込んだ割り下を使用し、少量のしょう油や砂糖で上品な甘さと旨みを際立たせています。

画像提供:はり重
最後に、文楽座三味線奏者の鶴澤寛太郎さん行きつけの「酒肴 哲」へ。なんば駅の東側に広がる「ウラなんば」エリアは飲食店が密集する活気ある夜の街の一つ。ここで営む「酒肴 哲」は、おでんを中心とした和食が楽しめる隠れ家的酒場です。

画像提供:酒肴 哲
「看板のおでんは、大阪らしいクジラのさえずりや牛すじに加え、ベーコンとクリームチーズの変わりダネ、ハモや湯葉など季節の味覚も楽しめます」と寛太郎さん。カツオとコンブの和出汁に鶏ガラスープを合わせた奥深いスープが、素材の旨みを引き立てます。
「どて焼き」は、白味噌と大阪の桜味噌を独自にブレンドし、熱々の状態で提供されるのもうれしいポイント。おでんとセットで必ず楽しみたい名物です。

画像提供:酒肴 哲
お好み焼 おかる
- 住所:大阪府大阪市中央区千日前1-9-19
道頓堀 今井 本店
- 住所:大阪府大阪市中央区道頓堀1-7-22
- ウェブサイト:道頓堀 今井 本店
はり重 道頓堀本店
- 住所:大阪府大阪市中央区道頓堀1-9-17
- ウェブサイト:はり重 道頓堀本店
酒肴 哲
- 住所:大阪府大阪市中央区日本橋2-7-27
- Instagram:酒肴 哲
上方芸能が映し出す、味わい深い大阪の歴史と文化
江戸時代に大坂で生まれ、それぞれ異なる魅力を持つ「上方落語」と「文楽」。どちらにも当時の暮らしや人々の息づかいが色濃く刻まれており、鑑賞や観劇とあわせて大阪の街を歩けば、上方文化の風情をより深く感じられます。上方芸能に触れて、ひと味違った大阪の旅へ出かけてみませんか?
- 記載の内容は2025年4月現在の情報です。変更となる場合があるのでご注意ください。
撮影:篠原沙織、田村和成
取材協力:上方落語協会、天満天神繁昌亭、文楽協会、国立文楽劇場、人形浄瑠璃文楽座